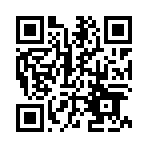2024年12月05日
晩秋の大窪寺へ
地区のいきいきサロンから声がかかり、晩秋の大窪寺へ。
参加者は15名、男女半々くらいかな。

先日のテレビで「紅葉が見ごろ」、と言っていたので「もう終わりかな」
そんな想いで出かけたが、まだ大丈夫だった、良かったね。
バスの道中でも山々の紅葉を楽しめる。
雑木は黄色や少し茶色っぽいのが多いが、それなりの風情がある。
そんな気がするね。

そして88番札所、大窪寺。
紅葉の下、本堂への階段をゆっくり上がりながら深まる秋を楽しむのもいいなあ。
日頃の疲れが取れる気がするよ。
本堂前、大きなイチョウは葉が落ちていたが、モミジはまだ残っていた。
まずは本堂でお参りし、景色を楽しむ。

標高770mの胎蔵ケ峰をバックに佇む本堂は趣があるね。
ここは四国88カ所参りの結願(けちがん)寺、お遍路さんもいたが、コロナ禍の影響か、僕がお遍路をしていた頃より人数は少ない。
でも中国人のグループにも会い、そこそこの人出。

ゆっくり歩くにはちょうどいいかな。
太子堂にもお参りし、大きな山門(右写真)も拝観、四国巡礼最後の寺にふさわしいどっしりとした構えである。
お昼は通りにある店で、結願いなり(赤飯入り)としっぽくうどんを頂く。
僕らは予約でスッと入れたが、当日客は10数人が並んでいたよ。

掘りごたつ式で足を入れられるのは楽でいい。
最近は減ったが、子どもの頃を思い出すよ。
ぬくいうどんは体があったまるわ、「ごちそうさまでした」
帰りには多度津町にある金陵の醸造所へ。
係の人から説明を聞きながら、所内を案内してもらう。
お酒と言えば、水が大事。
この地は八幡神社の森と隣り合わせで、涸れることのない湧水があり、中硬度の良水である。
八幡神社の森は夏になると蛍が飛び交う事で知られているよ。

お酒のできるまでは、11の工程がある。
衛生上の問題もあり、場内は一部しか見学できなかったが、彼の説明ともらった説明書である程度はわかるよ。

瓶詰め工程は見せてもらったが、そこへ入るにも靴の泥を落とすなど、やはり気を使っていたよ。
ちなみに「金陵」という名は、江戸時代の儒学者 頼山陽が琴平を訪ねた折り、中国の古都、金陵(代々帝王発祥の地南京)を思わせるものがあるとして、琴平を金陵と呼んだ事に由来するんだって。
創業は安政8年(1779年)、歴史ある酒屋さんである。
最後にお酒の試飲もさせてくれた。
「吟醸酒はうまいね」、数種類を試飲し、来年の正月はこのお酒をお神酒に。
そう思いつつ帰路についた。
この日は、日頃の作業などは忘れ、ゆっくりとした時間を過ごせたよ。
たまには息抜きをしなきゃ~ね
バスの運転をしてくれたドライバーさん、金陵の係の人、そしてプランを組んでくれた役員さんに感謝!
良き一日をありがとう!
参加者は15名、男女半々くらいかな。
先日のテレビで「紅葉が見ごろ」、と言っていたので「もう終わりかな」
そんな想いで出かけたが、まだ大丈夫だった、良かったね。
バスの道中でも山々の紅葉を楽しめる。
雑木は黄色や少し茶色っぽいのが多いが、それなりの風情がある。
そんな気がするね。
そして88番札所、大窪寺。
紅葉の下、本堂への階段をゆっくり上がりながら深まる秋を楽しむのもいいなあ。
日頃の疲れが取れる気がするよ。
本堂前、大きなイチョウは葉が落ちていたが、モミジはまだ残っていた。
まずは本堂でお参りし、景色を楽しむ。
標高770mの胎蔵ケ峰をバックに佇む本堂は趣があるね。
ここは四国88カ所参りの結願(けちがん)寺、お遍路さんもいたが、コロナ禍の影響か、僕がお遍路をしていた頃より人数は少ない。
でも中国人のグループにも会い、そこそこの人出。
ゆっくり歩くにはちょうどいいかな。
太子堂にもお参りし、大きな山門(右写真)も拝観、四国巡礼最後の寺にふさわしいどっしりとした構えである。
お昼は通りにある店で、結願いなり(赤飯入り)としっぽくうどんを頂く。
僕らは予約でスッと入れたが、当日客は10数人が並んでいたよ。
掘りごたつ式で足を入れられるのは楽でいい。
最近は減ったが、子どもの頃を思い出すよ。
ぬくいうどんは体があったまるわ、「ごちそうさまでした」
帰りには多度津町にある金陵の醸造所へ。
係の人から説明を聞きながら、所内を案内してもらう。
お酒と言えば、水が大事。
この地は八幡神社の森と隣り合わせで、涸れることのない湧水があり、中硬度の良水である。
八幡神社の森は夏になると蛍が飛び交う事で知られているよ。
お酒のできるまでは、11の工程がある。
衛生上の問題もあり、場内は一部しか見学できなかったが、彼の説明ともらった説明書である程度はわかるよ。
瓶詰め工程は見せてもらったが、そこへ入るにも靴の泥を落とすなど、やはり気を使っていたよ。
ちなみに「金陵」という名は、江戸時代の儒学者 頼山陽が琴平を訪ねた折り、中国の古都、金陵(代々帝王発祥の地南京)を思わせるものがあるとして、琴平を金陵と呼んだ事に由来するんだって。
創業は安政8年(1779年)、歴史ある酒屋さんである。
最後にお酒の試飲もさせてくれた。
「吟醸酒はうまいね」、数種類を試飲し、来年の正月はこのお酒をお神酒に。
そう思いつつ帰路についた。
この日は、日頃の作業などは忘れ、ゆっくりとした時間を過ごせたよ。
たまには息抜きをしなきゃ~ね
バスの運転をしてくれたドライバーさん、金陵の係の人、そしてプランを組んでくれた役員さんに感謝!
良き一日をありがとう!
Posted by 風(ふう) at 21:15│Comments(0)
│旅行、視察