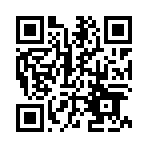2018年12月31日
年末に薪ストーブ点火
今年はいつもより暖かい、温暖化の影響かな。
(まあ、僕ら貧乏人にはありがたいのだが)
そして先日からやっと冬らしくなった。
薪ストーブの出番だ、27日の夜から使い出した。
いつものパターンでネコちゃんがのびの~び。
腹を出して寝てるのは安心しているからだろう。
毛むじゃらで、どこが顔だかわからない、って感じだけどね。
薪は勝手口を出た細屋(勝手口から門へ出て行く通路)に積み上げている。
その数、トロ箱で50個くらい。
その他は門を出た駐車場の裏、薪小屋。
以前は300m離れた畑の小屋まで軽トラで取りに行っていたが、今は一輪車で運べるようになり楽になった。
やはり近い方がイイね。
薪ストーブを初めて10年以上になるが、メリットは
①、燃料費がいらない。 自分で確保するから。
②、地球環境にやさしい。 温暖化の抑制。
③、部屋全体があったかくなる。
④、地下資源を使わず、再生可能エネルギー
ではマイナス面は
①、火事の危険性、(地震などの時スイッチ一つで消えない)
(火災報知器はつけています)
②、薪作りなどの手間とストック場所が必要。
それでもゆらゆら揺れる炎を見ていると、心まであったまる気がするんだなあ。
時間がゆっくり流れる、って感じ。
薪作り、これは人の考え方しだい、僕の場合、今回のような年末は別として、普段はやりたい時、というか時間が空いた時に適当にやっている。
一度にたくさんする必要もない。
我が家では薪ストーブは夜だけ、昼はみんなバラバラで食堂には一定時間しかいないんだ。
温度の調節は薪を入れる量と、煙突横のノブで中にあるダンパーの開閉。
右側の温度計で表面温度が200~250度位が適温、300度を超えるとやばいね。。
時には室温28度なんてこともある、 「ちょっと上げすぎたかな」
それとは別に、風呂も薪で焚いている。
五右衛門風呂ではなく、パイプでの循環式だ。
こちらは年中、なぜか主に僕の役目となっている。
炊事、洗濯はお願いしているのでこれくらいはしなければ、という気もあるしね。
最近は1年が経つのが早く感じる。
いったい何をやってたんだろう、と思う事もある。
でも、70才を過ぎた歳でまだやりたいことがある。
僕って欲張りかも。
来年は「やったぞ!」 と言える年にしたいね。
今年もあとわずか、無事一年間過ごせたことに感謝し、来年は有意義に暮らしたい。
一年間付き合っていただき、ありがとうございます。
みなさんにとって、「来る年が良い年でありますように!!」
2018年12月30日
僕流の薪作り
冬になると薪ストーブの出番。
その前に必要なのが薪作り、と言っても本当は1年以上前に作った薪を使用するから、生木を切ってすぐにとはいかない。
家の廃材とか大工さんにもらったある程度乾いた木は別だけどね。

そこで僕流の薪作りを紹介しよう。
人それぞれでやり方は色々だが参考になれば幸いだ。
僕の場合、薪の種類は2種類、自分で生木を切って作る物と、知人から頼まれた廃材など。
廃材は友人や知り合いから頼まれた時だけ、自分から「ください」とは言わないでも事足りるから。
廃材の長所は
①乾いているのでそのまま使える事。
②そんなに太いのは無く、電動ノコギリで切れる事。
③中には、まだ使えそうな柱や板などがあり、再利用できる事。
一方短所は
①、釘や金物が付いている事。
②、戸板や家具など大きくてカットしなければならない事。
③、合板などは接着剤など化学製品が使われている事。

時には釘を抜く事もあるが、普段は適当なサイズにカットし、釘は燃えかすの灰から取り出す。
その時役立つのが磁石式の釘拾い(マグネットキャッチャー)。
底面に磁石が付いていて釘などが引っ付く。

柄の上部にあるレバーを握ると離れ、釘は落下。
柄が長いので立ったまま作業が出来るのが良い。
これは廃材天国のJさんから教わり、ホームセンターで買った。
(元々は職人さんがこぼした釘などを拾うための道具らしい)
次に生木を使う場合。
僕は自家の畑にある生け垣や山の木を切ってストックしている。
長所は
①、自分で動けばタダで手にはいる事。
②,釘などは無く、灰はそのまま畑などに使用できる事。
③、たまに要らないか、と声を掛けられることもある。
短所としては
①、約1~1,5年乾燥させるので、すぐに使えない事。
②、中には直径30cm以上のもあり、チェーンソーで短く切って割らねばならない事。
僕の場合、直径10cm程度はそのまま輪切り、15cmは半割、それ以上は3つ割以上。
油圧式の機械は持っていないので斧で割る。

斧選びは形が2種類あり、おススメは右側の巾が広い物。
木を裂くように入っていく。
スパッと一回で割れた時は快感だね。
(これは土佐刃物、四国では有名だよ、値段は約1万円)
重さは柄を含め約3kg、この重さで割っていく。

柄の所に金具の当てが付いているとスカタンをくらった時でも柄が折れ難いのも良い。

太くてまたは堅くて割れない時はこんな方法もある。
クサビ(古い斧の頭を利用)を打ち込み、ハンマーで叩きながら割り込んでいく。
下手な鉄砲ではないが、大きな力が無くても数打ちゃ割れる。


盛り上がっていた野積みの薪もやっと片付き(上写真、前と後)、薪小屋も満杯状態。
2,3年分はあるよ。

正月前にサッパリできてホッとしている。
その前に必要なのが薪作り、と言っても本当は1年以上前に作った薪を使用するから、生木を切ってすぐにとはいかない。
家の廃材とか大工さんにもらったある程度乾いた木は別だけどね。
そこで僕流の薪作りを紹介しよう。
人それぞれでやり方は色々だが参考になれば幸いだ。
僕の場合、薪の種類は2種類、自分で生木を切って作る物と、知人から頼まれた廃材など。
廃材は友人や知り合いから頼まれた時だけ、自分から「ください」とは言わないでも事足りるから。
廃材の長所は
①乾いているのでそのまま使える事。
②そんなに太いのは無く、電動ノコギリで切れる事。
③中には、まだ使えそうな柱や板などがあり、再利用できる事。
一方短所は
①、釘や金物が付いている事。
②、戸板や家具など大きくてカットしなければならない事。
③、合板などは接着剤など化学製品が使われている事。
時には釘を抜く事もあるが、普段は適当なサイズにカットし、釘は燃えかすの灰から取り出す。
その時役立つのが磁石式の釘拾い(マグネットキャッチャー)。
底面に磁石が付いていて釘などが引っ付く。
柄の上部にあるレバーを握ると離れ、釘は落下。
柄が長いので立ったまま作業が出来るのが良い。
これは廃材天国のJさんから教わり、ホームセンターで買った。
(元々は職人さんがこぼした釘などを拾うための道具らしい)
次に生木を使う場合。
僕は自家の畑にある生け垣や山の木を切ってストックしている。
長所は
①、自分で動けばタダで手にはいる事。
②,釘などは無く、灰はそのまま畑などに使用できる事。
③、たまに要らないか、と声を掛けられることもある。
短所としては
①、約1~1,5年乾燥させるので、すぐに使えない事。
②、中には直径30cm以上のもあり、チェーンソーで短く切って割らねばならない事。
僕の場合、直径10cm程度はそのまま輪切り、15cmは半割、それ以上は3つ割以上。
油圧式の機械は持っていないので斧で割る。
斧選びは形が2種類あり、おススメは右側の巾が広い物。
木を裂くように入っていく。
スパッと一回で割れた時は快感だね。
(これは土佐刃物、四国では有名だよ、値段は約1万円)
重さは柄を含め約3kg、この重さで割っていく。
柄の所に金具の当てが付いているとスカタンをくらった時でも柄が折れ難いのも良い。
太くてまたは堅くて割れない時はこんな方法もある。
クサビ(古い斧の頭を利用)を打ち込み、ハンマーで叩きながら割り込んでいく。
下手な鉄砲ではないが、大きな力が無くても数打ちゃ割れる。
盛り上がっていた野積みの薪もやっと片付き(上写真、前と後)、薪小屋も満杯状態。
2,3年分はあるよ。
正月前にサッパリできてホッとしている。
2018年12月26日
只今植樹の準備中
来年は真平山会(まひらやまかい)ができて10年目、そこで記念の植樹を企画し、只今その準備中。
今年の春、桜の苗木助成という情報を得た。
これはチャンスと思ったが、本数が50本以上の条件。
「う~ん、ありがたいのだが今の参加者数で、はたして管理が出来るのか?」
スタッフが集まり話したが、少しムリでは・・・、断念した。
1周2,3kmの登山道を整備しながら、これまで100本以上の木を植えてきた。
今も管理は続いている、その上に50本は厳しいとの判断だ。
その後、インターネットで他の助成を見つけ申し込む、本数は20本とした。
この程度なら何とかなりそう、と思ったから。

結果は決まっていなかったが9月から行動開始。
と言うのも、予定場所は何年も放置され、雑木やバラなどが生えてすぐに植樹できる状態ではない。
ジャングルみたいで何処から入ろうか?、という感じ。
助成がダメだったら来年もう一度申し込む予定で動き出す。
植樹を行う時の準備としては
・予定地で邪魔な木の伐採
・草刈りなどと地ごしらえ
・苗木の手配 などである。

所有者の許可はもちろん得ているよ。
まず雑木が少ないヶ所から、高い木で10m位、本数も少なくやりやすかったが、それでも約ひと月かかった。
そして、次は放置30年と厄介なヶ所、木も15m以上、イバラやカズラも多い。(写真)
10月から2ヶ月以上かかり、やっと木の伐採を終える。
特に台風で木が倒れていたヶ所は、その上にカズラやイバラが生え手こずったよ。


こんな時は、やはり人数が多いとはかどるね。
木を切る人、草刈り、伐り木を引っ張り出し片づけるなど分担して行える。
11月に入ると、「助成が決まった」、との連絡あり。
「よかった!」、これで弾みが出るよ、うれしいなあ。
以前にも助成を受けた、「瀬戸内オリーブ基金」である。
「感謝!」

今月になり、苗木も届いた。
ある程度目処がついた、今年はここまで。
全部で長さ約200m、巾6mのスペースができたよ。

(右にポツンと見える白い軽トラの奥30mまでが予定地)
まだ太い木も放置しているが、片づけや地ごしらえなど、残りは来年やね。


(取りだした木の一部、この数倍ある)
植樹は子供たちにお願いし、体験してもらう予定だ。
今年の春、桜の苗木助成という情報を得た。
これはチャンスと思ったが、本数が50本以上の条件。
「う~ん、ありがたいのだが今の参加者数で、はたして管理が出来るのか?」
スタッフが集まり話したが、少しムリでは・・・、断念した。
1周2,3kmの登山道を整備しながら、これまで100本以上の木を植えてきた。
今も管理は続いている、その上に50本は厳しいとの判断だ。
その後、インターネットで他の助成を見つけ申し込む、本数は20本とした。
この程度なら何とかなりそう、と思ったから。
結果は決まっていなかったが9月から行動開始。
と言うのも、予定場所は何年も放置され、雑木やバラなどが生えてすぐに植樹できる状態ではない。
ジャングルみたいで何処から入ろうか?、という感じ。
助成がダメだったら来年もう一度申し込む予定で動き出す。
植樹を行う時の準備としては
・予定地で邪魔な木の伐採
・草刈りなどと地ごしらえ
・苗木の手配 などである。
所有者の許可はもちろん得ているよ。
まず雑木が少ないヶ所から、高い木で10m位、本数も少なくやりやすかったが、それでも約ひと月かかった。
そして、次は放置30年と厄介なヶ所、木も15m以上、イバラやカズラも多い。(写真)
10月から2ヶ月以上かかり、やっと木の伐採を終える。
特に台風で木が倒れていたヶ所は、その上にカズラやイバラが生え手こずったよ。
こんな時は、やはり人数が多いとはかどるね。
木を切る人、草刈り、伐り木を引っ張り出し片づけるなど分担して行える。
11月に入ると、「助成が決まった」、との連絡あり。
「よかった!」、これで弾みが出るよ、うれしいなあ。
以前にも助成を受けた、「瀬戸内オリーブ基金」である。
「感謝!」
今月になり、苗木も届いた。
ある程度目処がついた、今年はここまで。
全部で長さ約200m、巾6mのスペースができたよ。
(右にポツンと見える白い軽トラの奥30mまでが予定地)
まだ太い木も放置しているが、片づけや地ごしらえなど、残りは来年やね。
(取りだした木の一部、この数倍ある)
植樹は子供たちにお願いし、体験してもらう予定だ。
2018年12月16日
知っていますか?、香川県独立の父
知っていますか?、香川県独立の父。
実は僕もテレビで見るまで知りませんでした。
「そんな人がいたの?」、って感じ。
これはパネル展を見に行かなくっちゃ。

その人の名は、中野武営(ぶえい)である。
高松市の県立ミュージアム(玉藻公園の東隣)でじっくりパネルを見、資料もいただく。
例によって撮影は禁止(美術館などはこういうのが多い)。
故に写真は資料の一部から。
皆さんご存じの通り、明治になり「廃藩置県」で全国の藩はなくなり、県ができた。
香川でも明治4(1871)年に高松県が設置されたが、あとで徳島とつながり名東県に。
その後、香川県として1つの県になったが、今度は愛媛に編入され愛媛県の一部に。
そして、香川県として3度目の独立に貢献したのが中野武営。
彼は幕末、嘉永元年(1848年)に高松藩士の子として生まれ、才覚を表して高松県の官吏になる。

そして実力を評価され、中央官庁に登用、大熊重信(写真)など中央との人脈が出来る。
その後、愛媛県の県会議長となり、 明治21(1888)年、香川県の独立を実現させた。
一番遅く出来た県である。

それだけでなく、衆議院議員として7回当選、財政通として予算委員長にも就任。
中央でも才能を発揮したが、のちに「郵便制度の父」前島密(写真)の後任で鉄道会社の社長として実業家になる。
明治38年(1905年)には渋沢栄一の後任で東京商業会議所会頭に選出され13年勤める。
東京株式取引所の理事長にも就任した。(明治33年から12年間)

(左・中野武営、右・、渋沢栄一)
その他、緊張状態だったアメリカへ「平和の使者」として渡米し、大統領に会うなど日米親善に寄与する。
地元香川では、香川新報社(現、四国新聞)、第百十四国立銀行(現、百十四銀行)、讃岐鉄道(現、JR四国)、高松電気軌道株式会社(現、琴電)、

高松電灯株式会社(写真・現、四国電力)などの設立に関わり、黎明期の香川県や高松市の発展に尽力された人である。
以上、簡単に述べたが・・・、なぜ今まで県民に知られなかったのか?、少し不思議な気がする。
長い間、東京にいたからかも。
僕が思うに、郷土の発展に尽くした人として、地元の教科書に載っても、または教材として話が出ても良いのでは・・・。
興味のある方は、県立ミュージアムで見て下さいね。
会期は12月24日まで。
(僕の入手した資料はログハウスの本棚に置く予定でいます)
実は僕もテレビで見るまで知りませんでした。
「そんな人がいたの?」、って感じ。
これはパネル展を見に行かなくっちゃ。
その人の名は、中野武営(ぶえい)である。
高松市の県立ミュージアム(玉藻公園の東隣)でじっくりパネルを見、資料もいただく。
例によって撮影は禁止(美術館などはこういうのが多い)。
故に写真は資料の一部から。
皆さんご存じの通り、明治になり「廃藩置県」で全国の藩はなくなり、県ができた。
香川でも明治4(1871)年に高松県が設置されたが、あとで徳島とつながり名東県に。
その後、香川県として1つの県になったが、今度は愛媛に編入され愛媛県の一部に。
そして、香川県として3度目の独立に貢献したのが中野武営。
彼は幕末、嘉永元年(1848年)に高松藩士の子として生まれ、才覚を表して高松県の官吏になる。
そして実力を評価され、中央官庁に登用、大熊重信(写真)など中央との人脈が出来る。
その後、愛媛県の県会議長となり、 明治21(1888)年、香川県の独立を実現させた。
一番遅く出来た県である。
それだけでなく、衆議院議員として7回当選、財政通として予算委員長にも就任。
中央でも才能を発揮したが、のちに「郵便制度の父」前島密(写真)の後任で鉄道会社の社長として実業家になる。
明治38年(1905年)には渋沢栄一の後任で東京商業会議所会頭に選出され13年勤める。
東京株式取引所の理事長にも就任した。(明治33年から12年間)
(左・中野武営、右・、渋沢栄一)
その他、緊張状態だったアメリカへ「平和の使者」として渡米し、大統領に会うなど日米親善に寄与する。
地元香川では、香川新報社(現、四国新聞)、第百十四国立銀行(現、百十四銀行)、讃岐鉄道(現、JR四国)、高松電気軌道株式会社(現、琴電)、
高松電灯株式会社(写真・現、四国電力)などの設立に関わり、黎明期の香川県や高松市の発展に尽力された人である。
以上、簡単に述べたが・・・、なぜ今まで県民に知られなかったのか?、少し不思議な気がする。
長い間、東京にいたからかも。
僕が思うに、郷土の発展に尽くした人として、地元の教科書に載っても、または教材として話が出ても良いのでは・・・。
興味のある方は、県立ミュージアムで見て下さいね。
会期は12月24日まで。
(僕の入手した資料はログハウスの本棚に置く予定でいます)
2018年12月08日
冬じたく、薪小屋の改良
12月になってもまだ暖かい、昨日は少し寒かったけどね。
でも冬はやってくる。

梅雨までに片づけようと思っていた野積みの薪も放置したまま、夏場は太陽熱温水器で風呂が沸くため小屋の薪があまり減らず、ようやくスペースに空きができた。
そこで薪小屋の改良、ちょっとオーバーな言い方だが、本当は以前、畑にあった時の様に間仕切りをして、「先入れ先出し」が出来るようにする事。


まず今入っている薪を一旦外に出す、今回作業をする場所だけだよ。
スペースの4分の1位、出してみるとトロ箱(昔、魚を入れていた木の箱)で50もあった。
この中に薪を入れているのだ。(トロ箱も処分を頼まれたもらい物)
「多いなあ」と感じたが、この冬には使い切ってまだ足りない。
風呂もこれからは毎日焚くし、薪ストーブも使い出すと、1日に2,3箱使うからね。

次に北面の壁張り、今まではトロ箱を積んでいたので壁は不要だったが、今度はバラ積み、この方がたくさん入る。
いつも通り、材料の物色から・・・、桟木を打ち付けコンパネを張る。
寸法はちょうどといかないが、足らずは適当にあり合わせの板で補う。
あまり体裁にこだわらないのが僕流、実用本位だ。
人に見せる所じゃないからね。

そして肝心の間仕切り、間に柱を立てる、基礎はブロックだ。
ブロックの穴に合わせて柱の元をカット。
直接地面に着かないように13cm差し込む事にした。
ブロックの高さは19cm。 5cm地面に埋めると残りは14cmだから。

柱はもちろんストックしていた古材、使えそうな物は置き場所があれば残しておく、これが役に立つ。
柱を梁に固定する時、便利な工具がクランプ、鉄製で15cm巾まで固定できる。(左写真)
僕のように一人作業では重宝する。
2人だと「お~い、ちょっっと支えてくれ!」と言えるが、それができないからね。
柱が3本立つと桟木、これも適当に使えそうなのを見つけて取り付け、コンパネ張り。
これは安売りの時買って置いた物、足らずの一枚だけ買い足した。

最終的には3つの部屋に仕切り、乾燥の出来た順に使用していく予定だが、小屋の左側には、まだトロ箱150位残っているので、今回は間仕切り1つ分だけ。
あと1つ間仕切りを付ければ完成となる。

また今まではトロ箱を直接地面に置き底が腐っていたので、ブロックを置き、上に板を敷いて床上げ。
こうすれば腐らないしシロアリも防げる。
「薪からシロアリが出て、家をやられちゃった」、なんて笑っていられないからね。

(3つに分けた感じ、中央は取り出したトロ箱を戻した所)
最近は雨が多い、薪は2,3日乾かしてからの取り込みやね。

最後に東入り口の扉作り、吊り戸式で1枚は前回作っているのであと2枚。
もらい物の、コの字形の鉄板をカットし利用する。
軽い昔の戸に取り付け、上を引っ掛けて吊す。

レールはなし、部屋も3つ、戸も3つ、その都度必要な箇所だけ外し、中の薪を取り出す。
これで十分だ。
風呂は親の代から薪で焚いていた。
環境問題に関心を持ち、薪ストーブを導入して10年以上。
安物だが、まだ現役で役立っている。
(今年は暖かくまだ使用していない、これからだ)
僕が元気な間は薪の手配もできる。
そうでなくても、今は製材所や大工さんに声を掛ければ、冬以外は手に入るだろう。
僕の友人は解体屋さんから入手、これは置くスペースが必要となる。
狭い家では難しいかも。
エコである、しかも経費節減に繋がればもっとうれしい。
趣味でやるのは経費無視でもいいが、僕らはやはり安い方が良い。
ほどほどの物で楽しみながら出来ると一番やね。
興味のある人はチャレンジしてみては?
でも冬はやってくる。
梅雨までに片づけようと思っていた野積みの薪も放置したまま、夏場は太陽熱温水器で風呂が沸くため小屋の薪があまり減らず、ようやくスペースに空きができた。
そこで薪小屋の改良、ちょっとオーバーな言い方だが、本当は以前、畑にあった時の様に間仕切りをして、「先入れ先出し」が出来るようにする事。
まず今入っている薪を一旦外に出す、今回作業をする場所だけだよ。
スペースの4分の1位、出してみるとトロ箱(昔、魚を入れていた木の箱)で50もあった。
この中に薪を入れているのだ。(トロ箱も処分を頼まれたもらい物)
「多いなあ」と感じたが、この冬には使い切ってまだ足りない。
風呂もこれからは毎日焚くし、薪ストーブも使い出すと、1日に2,3箱使うからね。
次に北面の壁張り、今まではトロ箱を積んでいたので壁は不要だったが、今度はバラ積み、この方がたくさん入る。
いつも通り、材料の物色から・・・、桟木を打ち付けコンパネを張る。
寸法はちょうどといかないが、足らずは適当にあり合わせの板で補う。
あまり体裁にこだわらないのが僕流、実用本位だ。
人に見せる所じゃないからね。
そして肝心の間仕切り、間に柱を立てる、基礎はブロックだ。
ブロックの穴に合わせて柱の元をカット。
直接地面に着かないように13cm差し込む事にした。
ブロックの高さは19cm。 5cm地面に埋めると残りは14cmだから。
柱はもちろんストックしていた古材、使えそうな物は置き場所があれば残しておく、これが役に立つ。
柱を梁に固定する時、便利な工具がクランプ、鉄製で15cm巾まで固定できる。(左写真)
僕のように一人作業では重宝する。
2人だと「お~い、ちょっっと支えてくれ!」と言えるが、それができないからね。
柱が3本立つと桟木、これも適当に使えそうなのを見つけて取り付け、コンパネ張り。
これは安売りの時買って置いた物、足らずの一枚だけ買い足した。
最終的には3つの部屋に仕切り、乾燥の出来た順に使用していく予定だが、小屋の左側には、まだトロ箱150位残っているので、今回は間仕切り1つ分だけ。
あと1つ間仕切りを付ければ完成となる。
また今まではトロ箱を直接地面に置き底が腐っていたので、ブロックを置き、上に板を敷いて床上げ。
こうすれば腐らないしシロアリも防げる。
「薪からシロアリが出て、家をやられちゃった」、なんて笑っていられないからね。
(3つに分けた感じ、中央は取り出したトロ箱を戻した所)
最近は雨が多い、薪は2,3日乾かしてからの取り込みやね。
最後に東入り口の扉作り、吊り戸式で1枚は前回作っているのであと2枚。
もらい物の、コの字形の鉄板をカットし利用する。
軽い昔の戸に取り付け、上を引っ掛けて吊す。
レールはなし、部屋も3つ、戸も3つ、その都度必要な箇所だけ外し、中の薪を取り出す。
これで十分だ。
風呂は親の代から薪で焚いていた。
環境問題に関心を持ち、薪ストーブを導入して10年以上。
安物だが、まだ現役で役立っている。
(今年は暖かくまだ使用していない、これからだ)
僕が元気な間は薪の手配もできる。
そうでなくても、今は製材所や大工さんに声を掛ければ、冬以外は手に入るだろう。
僕の友人は解体屋さんから入手、これは置くスペースが必要となる。
狭い家では難しいかも。
エコである、しかも経費節減に繋がればもっとうれしい。
趣味でやるのは経費無視でもいいが、僕らはやはり安い方が良い。
ほどほどの物で楽しみながら出来ると一番やね。
興味のある人はチャレンジしてみては?