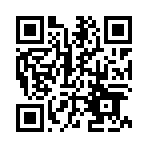2013年06月29日
梅とらっきょう、そしてミョウガ
今年も梅を漬ける。
焼酎は青梅、酢漬けは黄色く熟したもの。
そしてらっきょうも、Jさんからもらったのは畑から採ってきたまま。
ネギのような細い葉もついていた(右写真)が切り取り、水洗いして乾かす。
昨年2kg漬けたがみんなが食べ出し足らないので今年は4kg、不足分は買ってきた。
右から小梅、らっきょう、青梅、左端は焼酎に1年漬けたもの、色が変わり実も沈んでいる。
また新たにミョウガの酢漬け。
地区の花まつりで出店者に、「ビールのつまみにいいよ」 と勧められ1袋漬けた。
ひと月経つと食べられる。
味見して 「うまい」 と言ったら横から次々と手が出てきて、10日もするとこんなに減っちゃった。
最初はいっぱい入っていたのに。
ビールのつまみだから僕だけのもの、と思っていたら大きな見当違い、・・・
でもまあいいか、減るってことは、みんなが喜んでくれること。
変に納得した。
我が家ではらっきょうもじっくり3ヶ月~1年。
梅は1年おいてから食べ始める。
この方が味がしみておいしいから。
梅酒は3年おくと濃厚な味がするのだが、たいていそれまでに無くなってしまうのが現状。
3年ものも欲しいが、さばけて無くなるのもまた良し、だね。
去年作った梅酒ラックもいっぱいになり入りきらず。
(ここに12瓶入っている)
今はビンが20個ほどになったよ。
2013年06月26日
志々島、大楠と再会
今年も応援の依頼があり、25日に志々島へ。
昨年と同じく大楠の下草刈りである。
参加者は25名程度、僕たちは5名で参加した。
(写真、船には10数台の草刈り機を乗せて)
志々島は詫間の港から船で約15分、人口は20名ほど、この日は人口倍増だ。
島に着くと空き家の多い民家の間の路地を歩き、階段や坂道を通って山へ上がる。
大楠は峠を越して少し下りた所にある。
今回は島の頂上、三角点の所へも案内してくれた。
峠の三叉路から約15分、数カ所のアップダウンをして少し広い所が頂上、横尾の辻と呼ばれている。
三等三角点の印とエノキ、手作りのベンチもある。
ここまでの道と、この広場は島の人たちが切り開いたそう。
昭和60年頃はこのあたりまで畑があり手入れされていた(写真、左上。高い所が頂上)。
しかし人口の減少と共にだんだん荒れ、現在は道以外は山になりつつある。
あいにくのドンヨリした天気で周囲の景色はぼやけていたが、眺めの良い所だ。
引き返し、三叉路からすこし行くと「楠の倉展望所」。
この小屋も島民の手づくりだ。
島には車の走れる道がない、材料をここまで運ぶのは大変だっただろうなあ。
景色の良い所で、早めの昼食(写真)。
のどかな海を眺めながら。
のんびりしてていいネ。
さて本番の大楠はすこし下った所にある。
昨年みんなで苦労してつけた海岸までの道を重機が上がり、新しく3本の鉄製の支柱に支えられた楠の枝。
これで台風でも耐えられそうだ。
枝には樹齢を語るようにコケが生えている。
みんなが持ち寄った10数台の草刈り機、2600m2の面積もそんなに苦労はない。
ただし斜面が急なところもあり、足元には十分注意しながらの作業となる。
女の人も10名ほどいて、切った竹などの片づけ。
今年は楠の下の草刈りや竹切り程度だったので2時間くらいで終える事ができた。
ところでこの大楠、県の天然記念物であり、島のシンボル、守り神的存在。
幹の周囲が12m、枝を伸ばした面積が2565m2と大きい。
しかし、地面に近いところから枝が出てるのはなぜ?
クスノキって幹がまっすぐ伸び高い位置で枝分かれするのが普通だが・・・。
答えは土砂崩れで数m埋もれたため
それでも元気で生きているのがスゴイ!
この事は今年初めて知った。
(志々島では映画のロケもあった。、機関車先生、寅さんの男はつらいよ、など)
作業後はいこいの家で島民心づくしのお接待を受ける。
郷土料理の茶粥などをいただき、お腹も満足。
作業も無事終え、心も満足。
島の人たちに見送られながら、のんびりして交通事故の心配もない島を後にした。
「また来年も来るよ」 と約束して。
2013年06月24日
フルーツジャングル構想
ミカン畑の跡地をフルーツジャングルに。
以前にミカン農家廃業の事を記したが、畑の内15アール(450坪)をそれに当てたい、と思った。
この程度ではジャングルとはとても言えないが、面白そうなのであえてそう言おう。

(昨日収穫したスモモとビワ)
ヒントはアマゾン(ブラジル)のアグロフォレストリーとコンパニオンプランツ。
アグロフォレストリーとは、樹木を植栽し、樹間で家畜の飼育や農作物を栽培する農林業。
アマゾンではカカオ(チョコレートの原料)やフルーツなどの混植を行い人の生計と森も守れるので、「森をつくる農業」 ともいわれている。
今、アマゾンもハンバーガー用の牛の放牧場などで木を切られ荒れている中、この方法は良いと思っている。
一方コンパニオンプランツは農園でキャベツなど虫の寄ってくる野菜の畝や間にネギやレタスなど虫の嫌うものを植え、農薬に頼らず虫を寄せ付けないようにする方法。
組み合わせは野菜の種類によりいくつかあり、マリーゴールドなども利用されている。
ジャングルでなくても山へ行けばいろんな木が生えていて元気に育っている。
そこには多くの樹種があり、一種類の虫や病気が広がり難いのだろう。
それに比し、今の農業は同一種の野菜などをたくさん植える。
管理しやすいが、反面虫や病気も発生すると広がりやすい。
無農薬で多くの種類を育てるには混植が向いている、と僕は思った。

(小さなカキの実もついた)
そこまでの考えはなく、ミカンの木が枯れた所へ自給用の栗や梅などを植えてきたが、この際フルーツジャングルにする案が浮かんだ。
幸いこの畑には一抱え半ほどのクヌギや一抱えのモチノキなど周囲に10種類以上の木が生えている。
そして収穫可能な果物もクリ、柿、梅、スモモ、ミカン、ビワなど約10種類。
さらに増やし20種類くらいにするとおもしろそうだ。

(クリの花)
もっともジャングルのように混みすぎても実がならないし、風通しが悪いと虫や病気も発生しやすい。
一部は鳥のすみかとなる木も残したい。
ウグイスは毎日(声だけで姿はめったに見られない)、たまにキジとも出合うからね。
その中にある混植果樹園というのが妥当だが、「フルーツジャングル」 というネーミングにおもしろ味がある。

(ウメの実)
家族からは 「すこし変わっているお父さん」 と言われる僕だ。
こんな事をやっても、「また始まった」 で済むかもね。
以前にミカン農家廃業の事を記したが、畑の内15アール(450坪)をそれに当てたい、と思った。
この程度ではジャングルとはとても言えないが、面白そうなのであえてそう言おう。
(昨日収穫したスモモとビワ)
ヒントはアマゾン(ブラジル)のアグロフォレストリーとコンパニオンプランツ。
アグロフォレストリーとは、樹木を植栽し、樹間で家畜の飼育や農作物を栽培する農林業。
アマゾンではカカオ(チョコレートの原料)やフルーツなどの混植を行い人の生計と森も守れるので、「森をつくる農業」 ともいわれている。
今、アマゾンもハンバーガー用の牛の放牧場などで木を切られ荒れている中、この方法は良いと思っている。
一方コンパニオンプランツは農園でキャベツなど虫の寄ってくる野菜の畝や間にネギやレタスなど虫の嫌うものを植え、農薬に頼らず虫を寄せ付けないようにする方法。
組み合わせは野菜の種類によりいくつかあり、マリーゴールドなども利用されている。
ジャングルでなくても山へ行けばいろんな木が生えていて元気に育っている。
そこには多くの樹種があり、一種類の虫や病気が広がり難いのだろう。
それに比し、今の農業は同一種の野菜などをたくさん植える。
管理しやすいが、反面虫や病気も発生すると広がりやすい。
無農薬で多くの種類を育てるには混植が向いている、と僕は思った。
(小さなカキの実もついた)
そこまでの考えはなく、ミカンの木が枯れた所へ自給用の栗や梅などを植えてきたが、この際フルーツジャングルにする案が浮かんだ。
幸いこの畑には一抱え半ほどのクヌギや一抱えのモチノキなど周囲に10種類以上の木が生えている。
そして収穫可能な果物もクリ、柿、梅、スモモ、ミカン、ビワなど約10種類。
さらに増やし20種類くらいにするとおもしろそうだ。
(クリの花)
もっともジャングルのように混みすぎても実がならないし、風通しが悪いと虫や病気も発生しやすい。
一部は鳥のすみかとなる木も残したい。
ウグイスは毎日(声だけで姿はめったに見られない)、たまにキジとも出合うからね。
その中にある混植果樹園というのが妥当だが、「フルーツジャングル」 というネーミングにおもしろ味がある。
(ウメの実)
家族からは 「すこし変わっているお父さん」 と言われる僕だ。
こんな事をやっても、「また始まった」 で済むかもね。
2013年06月15日
駐車場づくり、待避場づくり
納屋の裏にある駐車場は間口が狭く奥が広い。
最初は1台しか置くつもりでなかったが、子供が帰ってきて車が増え2台置けるようにスペースを広げた。
しかし入り口は川、橋の所で広げられなかった。

おまけに道がカーブしていて、入り口は道に対しV形の鋭角で入れ難い。
子供からクレームが出ていたので今回修正することにした。
知り合いの業者に依頼し橋を6mほど広げるが、橋の下は施主(橋を架けた人)が掃除をする事になっている(これは水利組合の規則)
そこで3m毎にグレーチングを入れ、開けて掃除ができるようにした。
今回は2ヶ所である。
さて、それができ上がると駐車場側のカサ上げ。
ここの土は元水田のため石もなく良い土だ、このまま埋め込むのはもったいない。
その土を20cm程掘り出し他で使うことにした。
機械はないので手作業、一気にはいかない。
あまり広く掘ると雨水が溜まる、数区画に分け、堀だした所へ畑の土を入れ込む。
土掘りはエライ(しんどい)ね、半日やり、残り半日は他の作業をするって感じ。
自分でやるのでいつまでにって期限はないからね。
畑の土は道より高い所を削っていたが、50cmほど削った時、ふと閃いた。
「これは待避場にできるぞ」
この道は車が1台通るといっぱい、両サイドは畑で道より50cm以上高い。
子供たちも通学などで通る、待避場があれば車を交わせ安全だ。
よろこんでくれるだろう、一石二鳥の案である。

(左側の3角形状のヶ所が広げた待避場)
畑の岸なので土地が減るわけでもなく惜しげはない。
結果として、人が5,6人、自転車でも2台入れるスペースができた。
駐車場側は田との境に土止めの長石などを置いていたが拡張のため移動。
やはり機械はなく、バール(鉄の棒)とツルハシ、コロとテコの原理を応用し人力で動かす。

(右の黒っぽい線がバール、石の下はコロ)
長さ2m、200kgの石でもうまくやれば一人で動かせるんだよ。
要はやり方、僕のように腰痛持ちの者でもできる。
当然ながらサポーターを締め、慎重にやるけどね。

(ふち石を移動し並べ替えたヶ所)
下の土が軟らかくコロが回らないときは板を敷きその上にコロを置くと楽に動く。
厚い板がないときは角材を2本、レールのように並べ上にコロを置く。
実際にやってると色々知恵が湧くものだ。
二人だと300kgの物でも動かせるよ。
作業を始めて10日以上かかったが、ようやく土入れも終わった。

(右の草が生えている所が元のスペース)
以前に置いてた花崗土を上に敷きぬかるみを防止、花崗土はよく締まるからね。
不足分は業者に2トン車で運んでもらい自分で広げる予定。
ここまでやれば完成したようなもの。
夕食のビールがうまかったよ!
他人から見ると、「バカなことをやっている」 と思われるかも知れないが、自分でやろうと決めたものは続けていればそのうち出来る。
自分の気持ちしだい、早けりゃ良いってものでもない。
何かをする時、自分でするか、人に頼むか?
それは本人が決めること。
達成感を味わえるのは自分でやった方が数倍大きいね!
最初は1台しか置くつもりでなかったが、子供が帰ってきて車が増え2台置けるようにスペースを広げた。
しかし入り口は川、橋の所で広げられなかった。
おまけに道がカーブしていて、入り口は道に対しV形の鋭角で入れ難い。
子供からクレームが出ていたので今回修正することにした。
知り合いの業者に依頼し橋を6mほど広げるが、橋の下は施主(橋を架けた人)が掃除をする事になっている(これは水利組合の規則)
そこで3m毎にグレーチングを入れ、開けて掃除ができるようにした。
今回は2ヶ所である。
さて、それができ上がると駐車場側のカサ上げ。
ここの土は元水田のため石もなく良い土だ、このまま埋め込むのはもったいない。
その土を20cm程掘り出し他で使うことにした。
機械はないので手作業、一気にはいかない。
あまり広く掘ると雨水が溜まる、数区画に分け、堀だした所へ畑の土を入れ込む。
土掘りはエライ(しんどい)ね、半日やり、残り半日は他の作業をするって感じ。
自分でやるのでいつまでにって期限はないからね。
畑の土は道より高い所を削っていたが、50cmほど削った時、ふと閃いた。
「これは待避場にできるぞ」
この道は車が1台通るといっぱい、両サイドは畑で道より50cm以上高い。
子供たちも通学などで通る、待避場があれば車を交わせ安全だ。
よろこんでくれるだろう、一石二鳥の案である。
(左側の3角形状のヶ所が広げた待避場)
畑の岸なので土地が減るわけでもなく惜しげはない。
結果として、人が5,6人、自転車でも2台入れるスペースができた。
駐車場側は田との境に土止めの長石などを置いていたが拡張のため移動。
やはり機械はなく、バール(鉄の棒)とツルハシ、コロとテコの原理を応用し人力で動かす。
(右の黒っぽい線がバール、石の下はコロ)
長さ2m、200kgの石でもうまくやれば一人で動かせるんだよ。
要はやり方、僕のように腰痛持ちの者でもできる。
当然ながらサポーターを締め、慎重にやるけどね。
(ふち石を移動し並べ替えたヶ所)
下の土が軟らかくコロが回らないときは板を敷きその上にコロを置くと楽に動く。
厚い板がないときは角材を2本、レールのように並べ上にコロを置く。
実際にやってると色々知恵が湧くものだ。
二人だと300kgの物でも動かせるよ。
作業を始めて10日以上かかったが、ようやく土入れも終わった。
(右の草が生えている所が元のスペース)
以前に置いてた花崗土を上に敷きぬかるみを防止、花崗土はよく締まるからね。
不足分は業者に2トン車で運んでもらい自分で広げる予定。
ここまでやれば完成したようなもの。
夕食のビールがうまかったよ!
他人から見ると、「バカなことをやっている」 と思われるかも知れないが、自分でやろうと決めたものは続けていればそのうち出来る。
自分の気持ちしだい、早けりゃ良いってものでもない。
何かをする時、自分でするか、人に頼むか?
それは本人が決めること。
達成感を味わえるのは自分でやった方が数倍大きいね!
2013年06月12日
農を考える
今は野菜の育つ時季、トマト、キュウリ、ナスなど色々ある。
スイカはだいぶ伸びテニスボール大の実がなっている。
キュウリは初物を収穫し、写真はその後の実、ネットを張るのが遅くなっちゃった。
ナスも花をつけている。
サツマイモはツル差しだが活着し芽が増えだした。
敷きワラの代わりに刈草を敷いている、土の乾燥防止だ。
ツルが伸び出すと草を押さえてくれるので楽になる。
トマトは通常に耕した畝と自然農の地にも植えている。
ゴーヤも自然農、草にまみれ、どこにあるの?って感じ。
竹の支柱で目印、少し大きくなればネット張りだ。
カボチャも自然農、植える所を直径30cm位草削り、ちょこんと植えたら刈草で周囲を覆う。
耕さないので楽ちん
様子を見ながら牛ふん堆肥を施す。
やらなくてもある程度の実はなるが、妻はスーパーのと比較するのでやっている。
その辺は適当に、である。
この前、アイレックスで講演やディスカッションを聞いて考えさせられた。
その時、小出教授は 「農業など一次産業を大事にしたい」 と言っていた。
僕は自然農や有機農業を知ってから、今の慣行農業よりその方が良い、と思いながらやってきたが、いかに視野が狭かったか・・・。
日本の食料自給率が30%の今、大事なのは自給率を上げる事。
外国に振り回されず、自国で70%程度の自給率にする。
有機だの何だの、というのはその後に各自が適した方法を選べばいい。
「安心できる食料のl確保が第一」
それまでは農業者みんなが協力してやっていくのがいい。
愚かにも今頃になって気づいた。
妻によく言われる、「うちの野菜はよそのより小さい」
僕は化学肥料を使わない主義だが、それも臨機応変、その辺は適当にしようと思った。
無農薬は続けていきたいけどね。
タマネギは晴れているときに抜いて少し干し、持ち帰って吊す。
ジャガイモも収穫を始めた。
大きいのが入っていると妻が笑顔になる。
ソラマメは来年用の種取り(下の写真)。
こうして全部の種類ではないが自給自足。
一番いいのは、自分で作った無農薬野菜を安心して食べられること。
大地と火(太陽)、水、風、
自然の恵みに感謝の日々である。
2013年06月06日
アイヌの民、アシリ・レラさん
アイヌの語り部、アシリ・レラさんが廃材天国にやって来た。
彼女は二風谷の山ぎわに伝統的な茅葺きのチセ(家)や廃材で建てた家などで老若男女の人たちと共同生活。
身よりのない子の里親などの活動もしている。
今回は四国初上陸、10日間で8字状に4県のあちこちを廻り、6ヶ所で語り部やアイヌ刺繍のワークショップなどを行うとの事。
いろんな話をしてくれたが、悲しいかな僕の耳では半分ほどしか聞き取れなかった。
他の人は熱心に聞き入っていたよ。
(娘さんが着ていたTシャツのアイヌ模様)
そんな中、食を大切にすること。
人の体は食べ物によって成り立っている。
食べる事(自然のものを食す)を正しく行えばめったに病気にならない。
また、アイヌでは木の皮も薬味や薬として利用、その時も木の周囲の全部を剥がず3分の1だけ、そして皮が復元するようにする。
医食同源、身土不二的な話をしていた。
ちょうどS子さんが写真集を持っていて見せてもらうと、彼女の思いが。
大地のものは
いのちあるすべてのもののためにある
人間だけのもの
国のものはどこにもない
(食べ物などについて)
根っこを残して採るんだよ
同じ場所からばかり採らない
必要な分だけ採る
「自然を保護する」 なんて大それたこと
だって人間は自然の一部で
自然のなかで生かされているんだから
とぎれとぎれに聞こえた話と、この3つのことばを合わすと、先住民族の生き方や考え方、伝統を継承している彼女の姿が浮かんできた。
アシリ・レラ、それはアイヌ語で 「新しい風」
ネイティブアメリカンもそうだが、その人の役割(仕事)や特徴が名前となったものか?
残念ながら聞き損ねた。
自然と共に生きる、その生きざまを彼女から感じる。
そうなんだ、人間も自然の一部
おごらず、生かされているという謙虚な気持ちを忘れないように!
2013年06月01日
ナタネ収穫
4月に満開となった菜の花、だんだん茶色っぽくなり小鳥が実を食べに来だした。
少々ならいいが10羽以上が毎日来るとなると困るんだなあ。
また遅くなると種もはじけて落ちる。
梅雨には入ったが6月1日に刈り取りと決め、6日前にGさんに連絡。
それまでに少しでも草を刈っておこうとしたが、倒れていて手刈りのため思うようにできなかった。
4月に花が終わった後1度刈ったのだが草が生えるのは早いね。
今日、僕を含め3人の会員で作業を開始。
今年はコンバインの手配ができず、草刈り機での刈り取りである。
最初は刈ったナタネを横に払っていたがうまくいかず、ヘタをすると種を刃でちょん切ってしまう。
ここは筋蒔きをしてるので真ん中から左右に少しずつ刃を動かすとうまく倒れることに気づいた。
2人で刈り1人が集める。
全体を大きく3つに区切り、1区画を刈ると全員で集めて軽トラックに積み込む。
やはり草があると手間がかかるがナタネが大きく伸びている所はそれほどでもない。
しかし短い所は草と同じくらいの高さなので手間がかかるね。
2台の軽トラの左右にコンパネを立てらせ多く載せる。
ある程度入れると上から踏み込み盛り上げてできるだけ多く積む。
そしてシートをかけ豊中の倉庫へ移動。
午後は2名になりペースダウンしたが3時前になんとか終えた。
車で運んでいるとパラパラと雨、。
滑り込みセーフ、刈り取り中に降らなくて良かったわ。
全部で軽トラ4台分、倉庫にシートを敷き、広げて干したいところだが量がかなりあり、結局盛り上げるようになった。
下の方がムレたりカビたりするので、途中で上下ひっくり返す必要がありそうだ。
でも収穫を終え一段落ついた。
梅雨の雨はいつ降るか分からない。
ホッとしてこれを書いている。